こんにちは、アラフィフおっさん【ヒデ】です。
「値上げばかりで食費がキツい…」
「必要な物だけ買っているつもりなのに、毎月食費が高い…」
「節約したい気持ちはあるけど、忙しくて自炊なんて無理…」
こんな悩み、ありませんか?
実はこれ、**食費見直しチャレンジを始める前の“当時の私そのもの”**です(笑)
- 欲しい物・食べたい物を好き勝手に買っていた
- 予算を決めず、「欲しい=必要」で買い物していた
- 忙しいと言いつつ、家ではスマホやテレビに時間を使っていた
家計簿をつけて支出を見える化したことで、ようやく
- 大幅な赤字家計である実態を自覚
- 固定費の見直しに着手し、改善の土台を作り
- 変動費(特に食費)の予算を設定する大切さ
に気づきました。
▶︎ 結論:半年の食費見直しチャレンジで「月1万円の削減」に成功しました
2025年6月から始めた「食費見直しチャレンジ」。
半年取り組んだ結果、**食費は月平均44,000円 → 33,000円(▲11,000円)**に改善できました。
年々続く値上げの中で、以前より食材が高くなっているにも関わらず、
2023年31,000円、2024年35,000円という水準に近づいたのは自分でも驚きです。
さらに金額だけでなく食生活も大きく変化しました。
- 惣菜・半額食品中心の生活 → ほぼ自炊へ移行
- プロテイン、押麦、オートミールなど“健康寄り”の内容に
- 間食が減り体調面も改善
- 「無理な節約」をせずストレスなく続けられた
この記事では、半年間の取り組みを通して
- 何を見直したのか
- なぜ続けられたのか
- どんな変化があったのか
- 誰でも再現できる改善ポイント
をすべてまとめて紹介します。
食費がなかなか下がらない…
毎月の支出に振り回される…
そんな方の参考になれば嬉しいです。
過去の記事はこちら👇
食費見直しのスタート記事
最近の記事はこちら
なぜ私は食費を見直す必要があったのか?
私は総額2,000万円オーバーの借金を抱え、
毎月の家計は 約10万円の赤字 という、かなり危険な状態にありました。
まずは保険・スマホキャリア・光回線といった固定費の見直しを行い、支出の土台を整えました。
しかしそれでも家計はまだ赤字のまま。
次に目を向けたのが 「変動費」 でした。
被服費・書籍代・サブスク費なども見直しましたが、
やはり一番大きな割合を占めていたのが 食費。
ここを改善しない限り、黒字化は不可能だと感じました。
数字で見る当時の家計状況
私の当時の食費の平均は 約44,000円。
ちなみに単身世帯の平均食費では
- 全国平均:約47,000円
- 男性平均:約51,000円
- 女性平均:約41,000円(出典:総務省|家計調査2024単身世帯)
と、数字だけ見れば「平均的」に見えます。
しかし内訳が問題でした。
- 惣菜・弁当・半額シール品の常連
- 調理パン・レトルト・お菓子の購入が多い
- 自炊は週末だけ
- 栄養バランスは完全無視
- 予算も決めていない
- 「欲しいから」「食べたいから」で買う
平均値に収まっていたのは、
「お酒を飲まない」「外食をほぼしない」 この2つのおかげ。
もしどちらかをしていたら、間違いなく平均を大幅に超えていたと思います。
生活習慣の問題
「忙しくて自炊する時間がない」
そんなことを言いながら、実際は家に帰ってスマホやテレビを見る毎日。
仕事はありがたいことに忙しく、
朝から夜まで働いて 帰宅が21時を過ぎる ことも珍しくありません。
(今でもたまにありますが…💧)
平日は疲れすぎて自炊する気力はゼロ。
帰り道のスーパーで残った惣菜や弁当を買い、サッと食べて寝る生活でした。
朝はギリギリまで寝ていたため、コンビニでおにぎりやパン。
昼もパン。
栄養バランスを考える余裕はなく、
「お腹が満たされればそれでいい」食事を続けていました。
休みの日はその反動で
- 昼・夜は自炊するが大量に作って大量に食べる
- 10時、15時のおやつも好き放題
- 平日の鬱憤を休日の食事で発散
という感じで、結局はムダな支出と不健康のループでした。
最初に取り組んだ「固定費の見直し」が土台になった
食費見直しチャレンジは、家計全体のてこ入れの一環として始めたものです。
そもそも収入(予算)内に支出を収めるためには、まず “固定費を整えること” が最優先 でした。
そこで私が最初に取り組んだのが、以下の固定費の徹底見直しです。
実際に見直した固定費の内訳
■ 保険の見直し
- 内容が重複していた保険を整理
- 投資型の保険を解約し、必要最低限の掛け捨てに変更
→ 保険料が大幅に圧縮され、支出がシンプルに。
■ スマホキャリアの変更(au → UQ)
- 通信速度・電波の違和感はほぼなし
- キャリアメールはGmailへ集約して問題なく運用
→ 月額費用が大きく下がり、効果が出やすい見直しでした。
■ ネット回線の見直し(BBIQ → マネーフォワード光)
- 引越し時の手続きが簡単
- 更新・違約金の心配がほぼなくなる
→ 将来の手間まで軽くなり、精神的にもラクに。
■ 投資(資産形成)の見直し
- NISAは一旦ストップ
- iDeCoは毎月の拠出額を減額
→ 将来への不安から「とりあえず積み立て」ではなく、
まず目の前のキャッシュフロー改善を優先。
固定費見直しの成果は“59,000円の削減”という確かな結果に
これらの固定費見直しの結果、
月々59,000円の支出削減 に成功しました。
年間にすると 約70万円の改善。
これは、行動した人にしか得られない“圧倒的な固定費効果”でした。
そして固定費が整ったことで、
- 「次は変動費を見直して黒字化へ近づこう」
- 「家計に向き合う余裕が生まれた」
と、次のステップである “食費の改善” に集中できる土台が完成しました。
関連記事
固定費見直しの詳細はこちら👇
食費見直しチャレンジ半年の軌跡
ここからは、実際に私が半年間取り組んできた
「食費見直しチャレンジ」の具体的な内容を紹介します。
大事にしていたテーマは
“無理なく・続く・再現性のある方法” であること。
節約というより「生活の仕組みを整えた」結果、
自然と食費が改善していきました。
① 毎月の予算設定をルール化する
まず決めたのは、食費の予算を「35,000円以内」に収めること。
その中には お菓子代も含む ルールにしました。
- お菓子代の上限:月4,000円以内
- 単価:基本 200円以内
- 「質」か「量」かはその時の気分で決める
- 月1回の“ご褒美スイーツ”はOK(満足度を下げないため)
このルールを決めただけで、
「なんとなく買ってしまうお菓子」を確実に減らせました。
② 買い物の仕組み化
買い物は“戦略8割”です。
ここを整えたことで、ムダ買いと月末の赤字が激減しました。
■ 月初にまとめ買い(冷凍・日持ち食材)
- 冷凍野菜・冷凍肉
- 日持ちする調味料
- オートミール、コーヒーなど
→ 在庫が読めるので、食材が重なることがなくなった。
■ 週1回の生鮮・日配品のまとめ買い
- ヨーグルト
- 卵
- 納豆
- キムチ
- 豆腐
- 牛乳
→ 買い物回数が減り、ついで買いゼロの生活に。
■ 買い物するお店を“固定化”
月1買い物
- ラ・ムー:冷凍食品(肉・野菜)
- 業務スーパー:冷凍食品(野菜)
- コスモス:オートミール・調味料・インスタント味噌汁
週1買い物
・コスモス(上記の日配品)
買うお店・買う物・買うタイミングを
“決めておく”だけで、
判断疲れがなくなり、予算のブレも最小限になりました。
買い物ルールのメリット・デメリットまとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 事前に買う物と量を決めているので、悩まずに買い物ができる | 突発の出張・用事が続くと食材が余る可能性がある |
| 買い物回数が減り、ついで買い(=ムダ買い)が激減する | 追加の買い物をするとタイミングが崩れ、急な出費になりやすい |
| 在庫の把握が簡単で、冷蔵庫や冷凍庫の片付けが楽になる | メニューが“ガチガチ”になり、バリエーションが少ないと飽きる可能性がある |
| 期限内に使い切れる量を買うから食品ロスがなくなる | 固定化された献立が合わない人には少し窮屈に感じることも |
メリット・デメリットを理解しておくと
「続けやすい買い方」だけを自然に残していけます。
③ 自炊のハードルを下げる「ミニ習慣づくり」
料理が得意でも、凝った料理を作る必要はありません。
私が意識したのは “調理の頻度を減らす” ことでした。
- 1回の調理で 2〜3日分 を作る
- 冷凍保存できるものは 1週間分 作り置き
- 基本は レンジで簡単に作れるレシピに限定
- 平日の朝昼晩は ほぼ固定メニュー化(習慣にしやすい)
- プロテイン・サプリも活用し「手間をかけずに栄養補給」
- レシピ相談はAIに丸投げ
→「レンジのみ」「包丁なし」「10分以内」など条件指定が超便利
特にAIは、ネット検索とは違い
“今の自分に合ったレシピ”を提案してくれるので、
忙しいアラフィフ男性には本当に相性が良かったです。
④ 健康改善と食費削減のシナジー
食生活が変わったことで、
「ただ節約できた」以上のメリットがありました。
- 栄養バランスを意識するようになった
- 無駄食いが減った(満足度の高い食事ができている)
- 間食・お菓子の頻度が激減
- 眠気やだるさが軽くなった
- 食費は値上げラッシュの中でも 数年前と同じ水準 に抑えられた
“お金”も“健康”も一緒に改善することで、
生活の満足度がすごく上がりました。
数字で見る6ヶ月の変化
数字で振り返ると、今回のチャレンジの成果がよりはっきり見えてきます。
■ 毎月の食費の推移(2025年6月〜11月)
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 6月 | 34,971円 |
| 7月 | 33,592円 |
| 8月 | 27,218円 |
| 9月 | 32,395円 |
| 10月 | 32,946円 |
| 11月(15日時点) | 21,954円 |
6〜10月の5ヶ月平均は約33,000円。
チャレンジ開始前と比べて、月1万円前後の削減が安定して続いています。
年間換算では 約14万4,000円の改善。
これは固定費削減と合わせて、家計改善に大きな追い風になりました。
苦しかったポイント&乗り越えた具体策
半年間ずっと順調…というわけではありませんでした。
ですが「どう乗り越えるか」を決めていたことで、挫折せず続けられました。
① 仕事で遅くなった日・疲れた日の“手抜きOKルール”
- 帰宅が遅い
- しんどい
- 料理したくない
そんな日は 無理をせずにカップ麺・レトルト食品を活用。
「続けること」が目的で、ストレスを溜めないようにしました。
② 調理や買い出しが面倒な日の工夫
調理や買い物は単体でやると“やりたくない”が勝つ日が多かったので、
他の用事と組み合わせるようにしました。
- 調理しながら 本要約アプリを聴く
- 買い出しの前に ウォーキングとセット
- 休日の外出と 献血をセット
「面倒なこと × 楽しい/習慣化したこと」をくっつけるだけで、
不思議と行動しやすくなります。
続けられた理由
半年続けられたのは、根性ではなく 仕組みのおかげ でした。
① 予算という“わかりやすい目標”があった
35,000円という予算が明確だったので、
「今うまくいっているか」を判断しやすかった。
② 月末ではなく週単位で進捗を確認
- 月末に気づく → 大体手遅れ
- 週単位で気づく → 十分修正できる
この違いがめちゃくちゃ大きかったです。
③ 無理のない目標設定
目標は35,000円でしたが、
「まずは5,000円だけでも下がったらOK」
こんなスタンスで取り組んでいたので、ストレスがありませんでした。
④ ブログでのアウトプットが継続の原動力
チャレンジ内容をブログで発信していたため、
**「誰かが見てくれる」**という適度な緊張感がありました。
最初の月に無理なく達成できたことで
「これなら続けられるかも?」と自信を持てたのも大きいです。
まとめ|食費は“スキル”ではなく“仕組み”で改善できる
今回のチャレンジで実感したのは、
食費の見直しは「スキル」ではなく「仕組み」 だということ。
- 料理が得意じゃなくても改善できる
- やりくりの才能がなくても続けられる
- 節約ではなく「目標管理」にするとストレスがない
- 予算設定・メニューの固定化・AIの活用だけで十分改善できる
半年続けたことで、
食事や買い物は 生活の一部として自然に行える習慣 になりました。
次回予告
次回は「AIと共作舞台裏」シリーズです。
10月のAdSense不合格から、
次の申請に向けてどのように改善しているか、
裏側の取り組みをお届けします。
公開は11月22日(土)の夜の予定です。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!
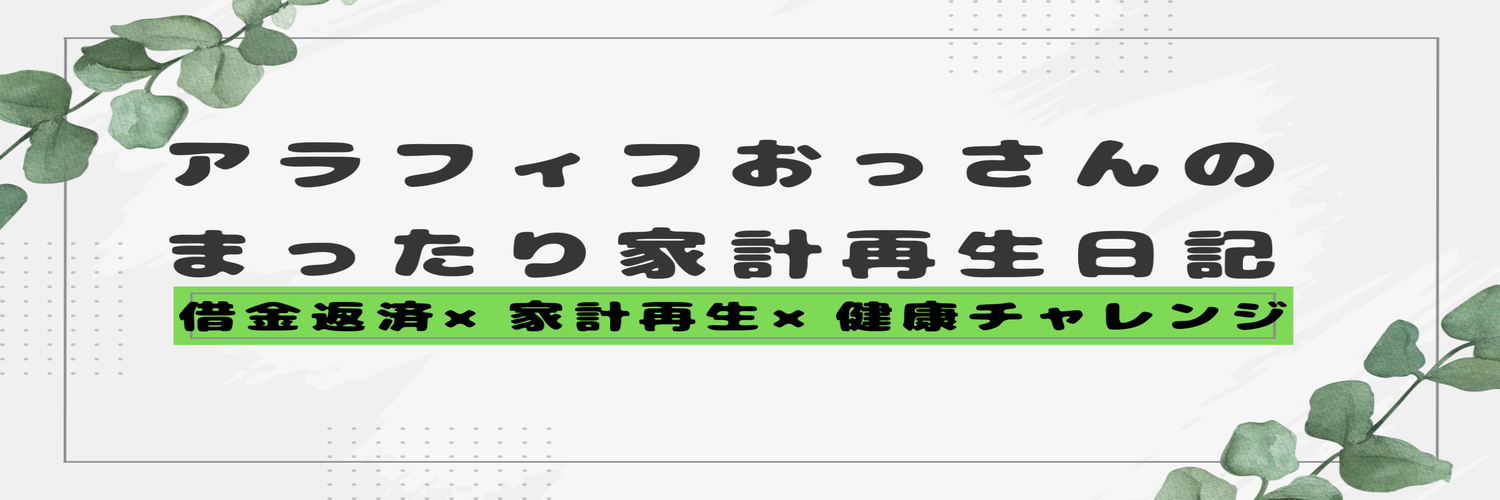
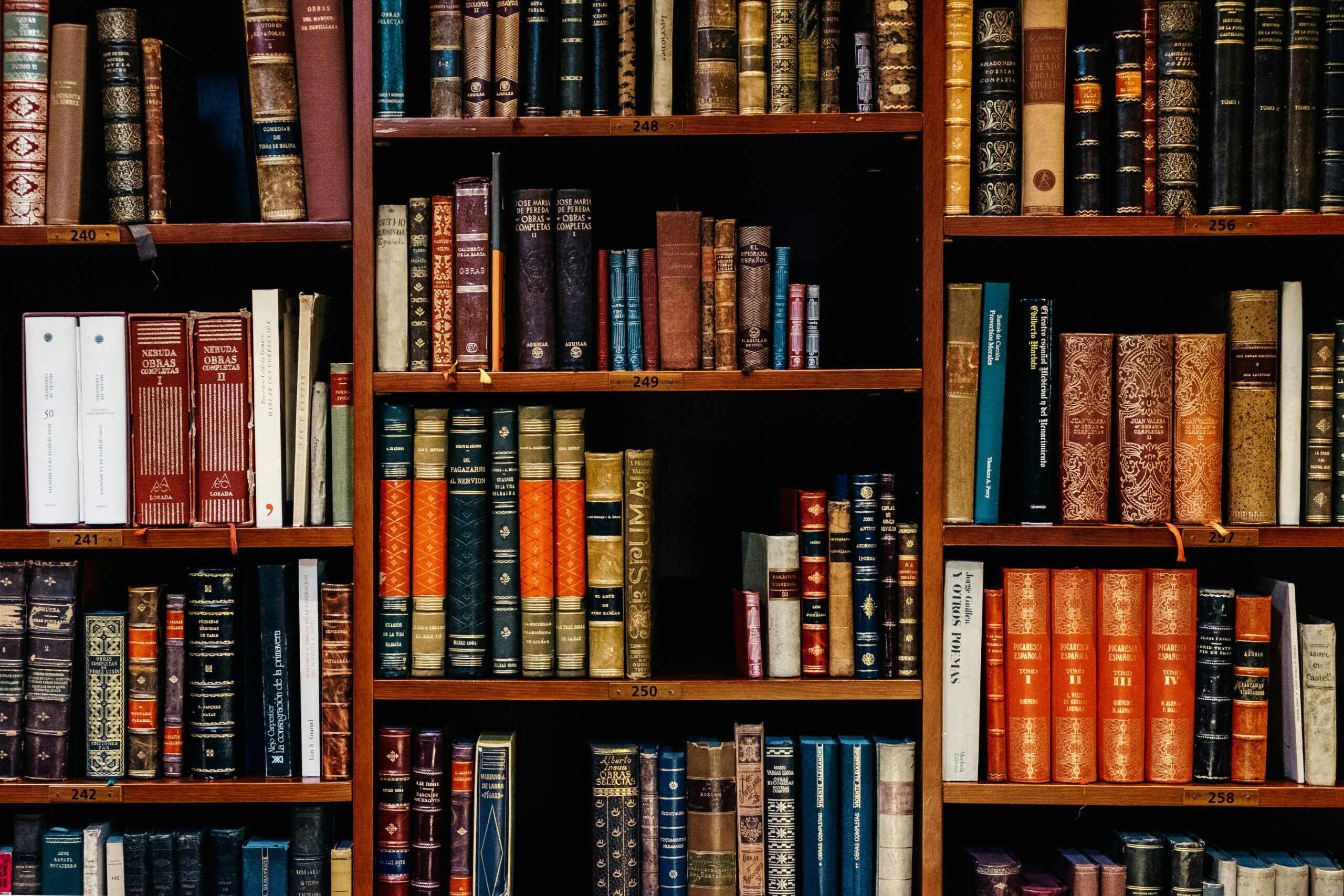

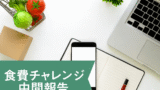

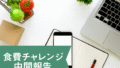

コメント